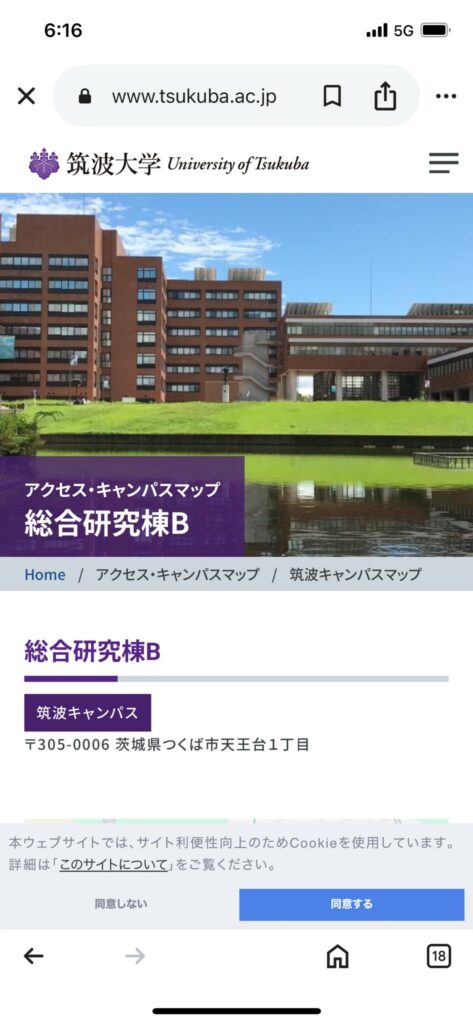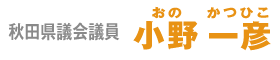令和7年8月8日(金)活動報告
インターバル速歩
7時20分から50分
つくばエキスプレスつくば駅前→筑波大学周辺
県道鳥海矢島線中直根バイパス交差部分舗装要望への対応報告あり
メールにて由利地域振興局建設部長さんより
市民、総合支所の皆様立会いにより丁寧な対応していただき感謝します。
筑波大学谷口先生を訪問、意見交換とアドバイスを受ける
14時半から15時半
○経緯
令和7年6月30日
秋田新幹線整備促進大会がメトロポリタン秋田で開催されました。
その際、筑波大学の谷口先生が基調講演をされました。先生は土木工学の研究者にして、心理学も研究されていらっしゃる。
モビリティ(交通)マネジメント(改善)で国内外の成功事例を研究されているほか、ご本人も成果を上げられています。
多くの場合、マネジメントを「管理」と訳す。しかし、この場合のマネジメントとは「改善」です。
例えば、行きすぎたモータリゼーションを改善し、バスや三セク鉄道の乗降客を増やすなど、交通改善をなしとげるためには、2種類に分類される方策がある。
①構造的方略
→法律などルールや予算などで実現を目指す。
②心理的方略
→利用者の意識を変え、自ら利用するような様々なコミニケーション施策を重視し実施する。
いわば、イソップ寓話の北風と太陽みたいなものかもしれません。
この基調講演終盤で、先生は、心理的方略の中で、市民の意識を変え、参画を促す、大きな力になるのは「目標に向かうナラティブ=物語を様々な市民が共有する→共感が生まれる→市民の紐帯を強くする→目標に向けた市民や事業者の、自分でできることがたくさん生まれる→目標実現に向けて社会が動き出す。とのお話をされた。
わたくしはこの先生のお話に強く感銘を受けました。ナラティブの共有が市民の紐帯を強くする。この戦略、プロセスは、交通の改善はもちろん、秋田県が強く進めようとしている子育て世帯のAターン対策にも応用できるのではとも考えました。
そして、どうしても先生に直接お会いし、意見交換とそうしたことについて教えていただきに、筑波大学にお伺いしました。
その前提として、先生のご著書を購入し、事前勉強しました。
行動変容をうながすアンケートの手法や市民や事業者と直接対話を繰り返すことで信頼関係と新たな効果的な施策を生み出すことを事例で学びました。
帯広市のバス利用者が増えたプロセス、明石市のコミュニティバスが利用者を増やした取り組み、中心市街地での買い物客を増やした成功事例などを学び、対話に臨みました。
秋田県に戻り就職する方を増やすために、先生から教えていただいた、モビリティマネジメントの手法を生かすことが、できるのではないか。先生がかかわり、現在も取り組んでいらっしゃる事例、ポイントを丁寧に教えていただきました。
そして、貴重な資料もいただきました。
前日に続き非常に有意義な調査となりました。
新幹線移動
この日は最終の秋田新幹線で大曲駅でおり、東由利に着いて、0時過ぎ。
新幹線内では由利本荘市に出された大雨の、警戒レベル5の情報が入りラインで情報交換しながら帰宅しました。
泉谷市議はじめ、夜遅くまで情報いただきありがとうございました。